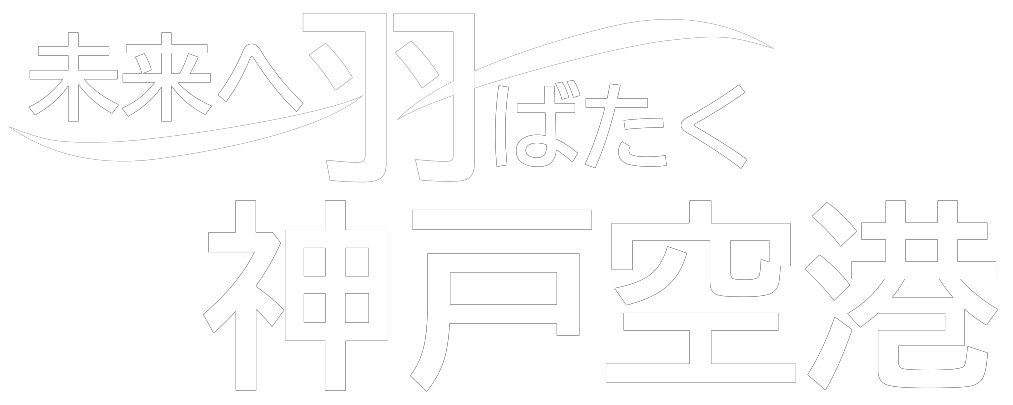年明け早々に発生した日本航空と海上保安庁の航空機衝突事故が記憶に新しい中、年の瀬にも多数の犠牲者を出す航空事故が韓国・務安で発生した。
同じ職に就く者として、今回の航空事故の所感を書き綴るとともに、亡くなった乗客乗員全員に対して哀悼の意を表したい。
事故の概要

今回、事故が起きたのはチェジュ航空のB737-800型機。韓国の務安国際空港へ胴体着陸を試み、滑走路をオーバーランして滑走路外の障害物に衝突し炎上。乗客乗員179名の尊い命が失われた。
事故機が胴体着陸に至った原因はまだ明らかとなっていないが、着陸直前にバードストライクが発生していたと報道されている。(胴体着陸との因果関係は不明である。)同型機は日本の航空会社でも広く使用されているロングセラー機であり、不具合が頻発している機体ではない。
ダイバートという選択肢は?
今回、チェジュ航空機が胴体着陸を行ったのは元々の目的地である務安国際空港。同空港の滑走路長は、国際空港としては短い2800mで、この滑走路長も悲惨な結末を生んでしまった一つの要因ではある。
そのため、ネット上などでは長大滑走路(3500〜4000m滑走路)を持つ仁川国際空港へダイバート(目的地変更)するべきだったという様な声も聞かれた。しかし、務安から仁川までは比較的距離があるため、残燃料の観点で仁川には向かえなかった可能性が高い。特に、今回の当該便はタイからの国際線であり、短距離機材のB737では潤沢に燃料を積むことは難しい。(もし、仁川に行くための燃料が残されていたとしても、電源喪失・油圧喪失・電気火災等が起きていた場合には、一刻も早く着陸することが求められる。)
また、今回の事故機はフラップ※が下りていなかった可能性も指摘されている。その場合には滑走路への進入速度が相当速くなるため、長大滑走路に着陸していたとしてもオーバーランしていた可能性は否定出来ないのだ。(B737のような小型機であっても、フラップや制動装置の不作動状態での着陸は3000m以上の滑走路長が必要になることがある。)
※フラップ⋯高揚力装置のこと。離着陸時は飛行機の速度を落とす必要があり、小さい速度で揚力を得るためにフラップを下ろす必要がある。フラップの他にも、主翼前面にはスラットと呼ばれる高揚力装置も装備されている。

何故ギアは下りなかったのか?
旅客機のギア(車輪)は通常、油圧装置によって上げ下げする仕組みとなっている。そのため、油圧系統が不作動となった際には、通常のギア操作は出来ない。
しかし、ギアは飛行機の着陸には欠かせない重要な装置であり、万が一の事態に備えて油圧以外にギアを操作する(下げる)機構も備わっている。これは、ギアの自重を利用してギアを下げるもので、事故機であるB737も例外ではない。
今回のチェジュ航空機はギアを出さず胴体着陸に至っている。油圧以外の代替手段を用いてもギアを下げられないという通常では考えられない状況に陥っていた可能性があるのだ。
ちなみに、先程触れたフラップも油圧系統が関与するシステムである。そのため、ギアに加えてフラップも下りていなかったという状況を鑑みれば、油圧系統(もしくは油圧を制御する電気系統)には何らかの不具合が生じていた可能性は高い。
胴体着陸はどのパイロットでも至難の業
我々パイロットは、飛行機に緊急事態が発生した状況を模擬し、シミュレーターで定期的に訓練・審査を受けている。ここで取り扱われる緊急事態とは、片側エンジンの不作動・与圧装置の故障・空中火災など多岐にわたるのだが、あらゆる事態をシミュレーターで再現できるわけではない。
今回発生した胴体着陸(ギアが出ない状態での着陸)についても、飛行機のマニュアル・航空各社のマニュアルにはその対処法が記載されている。しかし、シミュレーターでの状況再現には限界があるほか、起きる可能性の低さから不時着・不時着水等は普段の訓練・審査では取り扱われない。
今回は「バードストライクが発生」「ギアが全て出ない」「フラップが出ない」という状況が全て同時に発生したとみられている。パイロットは定期的に訓練・審査を受けているとはいえ、これらの災難が同時に発生した場合には非常に困難な事態に陥るのだ。
今回の事故を捉えた動画には、滑走路上を滑りながらもパイロットが機首を上げ続けている様子が残されている。各飛行機メーカーのマニュアルには、前輪が出ない状況での着陸は可能な限り機首を浮かせるように操作手順が定められており、パイロットが必死に機体をコントロールしようとしていた様子は動画からも見て取れる。
2800m滑走路への着陸を試みるのではなく敢えて着水を決断する、胴体着陸後に機首を敢えて滑走路に擦り付けて減速を試みるなど、他にも手段はあったのではないかと思うところはある。だが、そのような論評は後付け論でしかない。
今後、事故機に残されたフライトレコーダー等を元に事故調査が進むことになる。「絶対」は存在しない飛行機の世界で、過去から得られる教訓は非常に重要である。事故の原因究明が進み、得られた教訓が今後の航空機の安全運航に繋がることを期待したい。